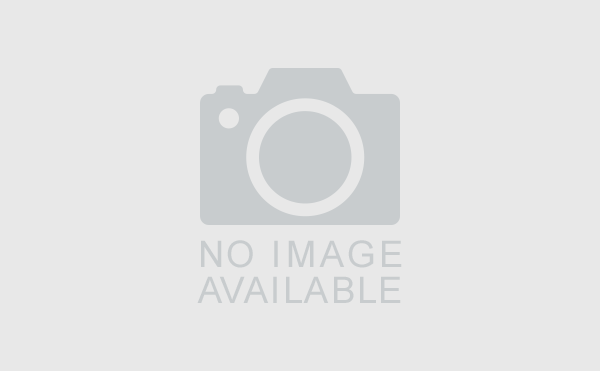嚥下障害食事介助の“NG習慣”と今すぐできる見直しポイント

嚥下障害と食事介助の基本知識
嚥下障害とは?症状・原因・患者の特徴を解説
嚥下障害とは、食べ物や液体を口から咽頭、食道へ送り込む過程(嚥下)がうまく行えなくなる状態です。これは単なる高齢化による筋力低下だけでなく、脳卒中やパーキンソン病、認知症、頭頸部のがん治療後など、さまざまな障害が原因で起こります。嚥下障害の患者さんには以下のような特徴が見られます:
- 食事中にむせる、咳き込む
- 飲み込みに時間がかかる
- 口腔内に食べ物が残留する
- 声がガラガラする
- 食欲低下による体重減少
嚥下障害を放置すると、食事や水分摂取が十分に行えず、誤嚥性肺炎や低栄養、脱水といった深刻な健康問題を招きます。
食事介助が必要となる理由とその役割
嚥下障害の患者さんにとって、食事介助は単なる「食べさせる作業」ではありません。嚥下の機能を補助し、誤嚥を防ぐ大切な命の支援です。とくに高齢者では、咽頭や頸部の筋力低下により誤嚥リスクが高まるため、介助者が正しい方法で支えることが不可欠です。
E-E-A-Tの観点でも、医師や言語聴覚士(ST)、看護師、介護士など専門職の連携と経験が患者さんの安全を大きく左右します。誤嚥のリスクを低減し、患者さんが安心して食事を楽しむためには、専門的知識と現場経験に基づく適切な介助が必要です。
高齢者に多い嚥下障害の現状とリスク
日本は超高齢社会を迎え、高齢者の嚥下障害は年々増加しています。加齢に伴う筋力低下だけでなく、脳神経疾患や慢性疾患が嚥下に影響を与えます。嚥下障害が進行すると、以下のリスクが高まります:
- 誤嚥性肺炎
- 栄養不足
- 脱水
- 窒息
こうしたリスクは生活の質を著しく低下させ、最悪の場合は命にかかわるため、早期発見と正しい介助が極めて重要です。

食事介助でよくある“NG習慣”10選
嚥下障害の食事介助現場では、多忙さや慣れによる「NG習慣」が意外に多く見られます。以下は特に注意すべきポイントです。
患者の姿勢を無視した介助
嚥下障害の介助で最も大切なのは「姿勢管理」です。ベッドに寝かせたまま介助を行うと、咽頭への食べ物の流れが乱れ誤嚥しやすくなります。必ず頸部をやや前屈させた座位を保ち、摂食をサポートしましょう。
適切でないスプーンの使い方・入れ方
スプーンを口腔奥へ突っ込みすぎたり、急いで押し込む介助は絶対NGです。誤嚥を誘発するだけでなく、患者さんに強い恐怖感を与えます。スプーンは軽く口元に当て、患者さん自身が取り込むのを待つのが安全です。
食事形態やとろみ調整の不足
嚥下障害の患者さんには、食べ物の形態やとろみの調整が必要です。調整が不十分だと、液体が咽頭へ流れ込み誤嚥を引き起こす可能性があります。食事形態は患者さんごとに見極める必要があります。
一口量やひと口の大きさに対する配慮不足
嚥下障害患者さんに大きなひと口を与えるのは危険です。咽頭の反射が間に合わず誤嚥や残留を引き起こすことがあります。ティースプーン一杯程度が目安です。
食事中の話しかけ・刺激など環境管理のミス
介助中、過度に話しかけたり周囲が騒がしいと嚥下動作が乱れます。摂食に集中できる静かな環境作りが大切です。
水分摂取の方法・タイミングの誤り
嚥下障害の患者さんは、水分摂取にもとろみが必要な場合が多いです。さらさらした液体は誤嚥を招きやすいため注意が必要です。
食後すぐの体位変換や寝かせ方
食後すぐに仰向けに寝かせると、食べ物や唾液が逆流し誤嚥しやすくなります。最低30分は座位保持が原則です。
食事介助中の観察・異変対応の怠り
むせたり、声が変わるなど異変を見逃すのは危険です。些細な変化でも専門家へ相談する姿勢がE-E-A-Tの観点からも重要です。

今すぐ見直せる!嚥下障害 食事介助の改善ポイント
正しい姿勢とポジショニング法(前屈・座位・頸部安定など)
嚥下障害の患者さんには頸部前屈位(顎引き姿勢)が効果的です。咽頭への食べ物の誤流入を防ぎ、誤嚥リスクを減らせます。座位が難しい場合は30度以上のベッドアップを心がけます。
食事メニュー、食品・市販品選びと形態の工夫
- ムース状やゼリー状食品を活用
- 市販の嚥下食を取り入れる
- 咽頭に残留しにくい形態を選ぶ
市販品にはユニバーサルデザインフード(UDF)など嚥下障害向け製品も多く、選択肢が豊富です。
とろみ・ゼリーなど摂食を助ける食事の工夫
嚥下障害では液体にとろみをつけるのが基本です。とろみ剤は製品ごとに粘度が異なるため、必ず指示通りに調整します。ゼリーも分離しないものが推奨されます。
スプーンや食器類の選び方と使い方のポイント
- 小さめのスプーンを使う
- 口腔に軽く触れさせ、患者さん自身が取り込むのを待つ
- 角度調整が可能な食器も便利
一口量・ペース配分の適切なサポート方法
- ティースプーン1杯程度が目安
- 患者さんの嚥下が済むまで待つ
- 疲労やむせのサインを見逃さない
安全な水分補給・誤嚥防止の工夫
とろみ付き水分は必須であり、むせやすい患者さんにはゼリー飲料が有効です。水分摂取も姿勢保持を徹底しましょう。
食事介助の流れと手順~実践ガイド~
食事前の準備と患者状態の観察・記録
食事介助前には以下を確認します:
- 意識レベル
- 呼吸状態
- 痰の有無
- 口腔内の残留物
記録はチームで共有し、次回以降の介助に活かします。
経口摂取の進め方と必要時のサポート
経口摂取は「少量から」が基本です。誤嚥が疑われる場合は中止し、専門職へ相談します。患者さんの摂食能力をよく見極めることが重要です。
食後のケア(姿勢維持・口腔ケア・観察)
- 最低30分の座位保持
- 口腔ケアで誤嚥性肺炎予防
- 呼吸音や声の変化に注意
介助における看護師・介護士の連携と役割分担
- 看護師:嚥下評価や医療判断
- 介護士:日常介助の観察・記録
- チーム全体で情報共有し、誤嚥防止につなげます
食事介助中に気をつけたい“注意点”と早期対応
誤嚥・窒息・残留の危険性と観察ポイント
むせ、咳、呼吸音の変化は誤嚥のサインです。咽頭や頸部の動き、顔色の変化も注意深く観察しましょう。
患者ごとの障害程度や必要な工夫の見極め
嚥下障害の程度は患者さんごとに異なります。画一的対応は危険です。必ず専門家と連携し、個別の対応を心がけましょう。
摂食嚥下障害リスクへの対応と訓練方法
嚥下リハビリはST(言語聴覚士)が専門です。以下の訓練が行われます:
- パタカラ体操などの発声訓練
- 頸部前屈嚥下法
- 咽頭や口腔の筋力トレーニング
Q&A:よくある疑問・困りごとFAQ
嚥下障害の治し方や訓練法は?
嚥下障害は原因によりますが、訓練で改善するケースも多いです。自己流は危険なので必ず医師やSTの指導を受けましょう。
市販の嚥下食やとろみ剤の選び方・注意点
とろみ剤はメーカーごとに粘度が異なるため、専門職の指示に従うことが大切です。市販の嚥下食は「UDF」マークを参考に選ぶと安心です。
家族・介護者が安全に介助するためのポイント
- 患者さんの姿勢管理を徹底
- 無理に急がせない
- 異変を見逃さず専門家へ相談
まとめ:嚥下障害患者の安全・安心な食事介助のために
嚥下障害の患者さんへの食事介助は、単に食べ物を口に運ぶだけの行為ではありません。誤嚥を防ぎ、命を守るための極めて重要なケアです。正しい姿勢やスプーンの使い方、とろみや食事形態の工夫を行い、異変にすぐ気づく観察力を磨くことが大切です。
E-E-A-Tの観点からも、専門家の知識・経験を活かし、チームで支える介助が患者さんの安全とQOL(生活の質)を高めます。大切なのは「焦らず、個々に合わせ、丁寧に」。誤嚥の不安を軽減し、患者さんが再び「食べる喜び」を感じられるよう、一つひとつの介助を見直していきましょう。